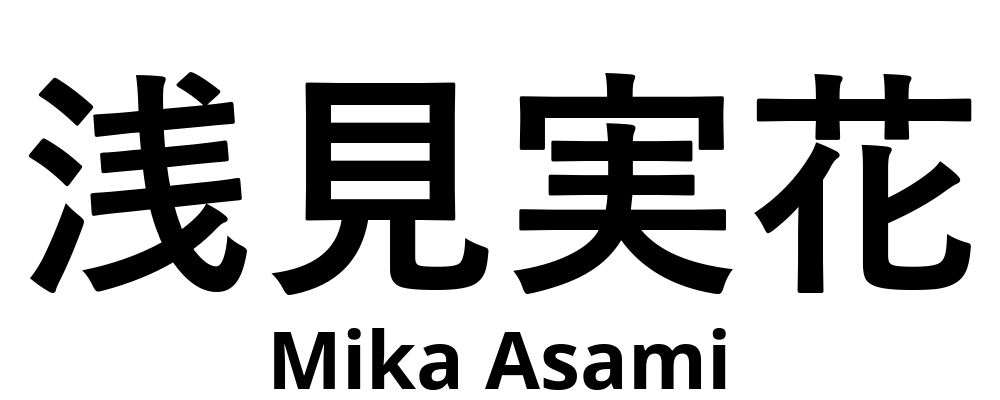アフリカへサファリに行く
ンゴロンゴロ編(1)
アフリカへサファリに行く
ンゴロンゴロ編(1)
マサイたち
夜明け頃、目が覚めてベッドを降りる。Tシャツでは肌寒い。外の気温はかなり下がっているだろう。
フリースを着込み、カメラを持って、テントのジップを押し上げる。
空気はまだ冷たいが、澄み渡って気持ちがいい。そこら中で鳥や虫たちが騒いでいる。
空は朝焼け。濃紺とオレンジ色のグラデーション。

テントの先は、緑の濃い草木が林のように生い茂り、奥へ奥へとつづいている。
この空間にどんな生き物が隠れているだろう?
私はそれらが肉食ではないことを祈りつつ、テントの入り口、自分の退路を背中でしっかり感じ取る。
ふと視線がかなたのアカシヤに届いた瞬間、ニョキッと突き出た黒い影が、木と木の隙間で動いているのを発見する。アカシヤの葉が好物の、首の長い彼。
「どう、昨夜はよく眠れた?」
日が昇り、メインテントで朝食をとって、私たちは出発する。
「僕もぐっすり眠ったよ」
この48歳のサファリガイドはいつもとびきり元気なのだ。
朝食には、イスラエルからきた夫婦(退職して世界中を旅している)と、アメリカ人の女性が1人(コロラド州出身でアフリカに魅せられる)と隣り合った。年齢は60を超えているが、身体はとても丈夫そうで好奇心にあふれている。首からはもちろんカメラをぶら提げて。ゴツゴツとした本格的な高級カメラ。
「次は是非、日本に行きたいと僕らは思っているんだよ。日本の文化にとても興味があるんだ」
イスラエリの老紳士が輝く瞳で私にコメントを求めてくる。
いよいよ、私たちのサファリカーは、最後の目的地「ンゴロンゴロ自然保護区」へ向けて出発する。
ンゴロンゴロは、セレンゲティに隣接するタンザニア北の自然保護区で、その面積はおよそ8,300km2。果てしなく拡がる平原・セレンゲティの6割だ。
ンゴロンゴロはマサイの言葉で、牛の提げるベルを真似た音、そして「大きな穴」の意味を持つ。穴というのはクレーター。
このエリアには、3百万年前の大噴火で形成されたクレーターが3つあり、なかでも最大のクレーターは「動物たちの楽園」として多種多様な野生生物をその懐に抱いている。
また、エリア内の「オルドヴァイ渓谷」には、噴火によって閉じ込められた人類初期の二足歩行の足跡や化石などが発見され、「人類発祥の地」として有名だ。この渓谷の存在は、太古の昔この土地で動物と人類が共存していたありようを教えてくれる。マサイとは、その人類的な原風景を、何百万年という長い長い歳月を経て、現代の世に引き継ぐ種族なのだ。

しばらく走ると、まわりをぐるりと地平線に囲まれる。
背景は「ヌー、ヌー、シマウマ」、「ヌー、ヌー、シマウマ」、繰り返し。
ようやくヌーが少なくなったと思う頃、道端の地面の上で、人が倒れているのを発見する。たまたまスマホで動画を撮っていた私は、仰天してビデオを止める。
あたり一面、どこを向いても人のいないこの土地に、ガリガリに痩せた男がまっすぐ伸びて固まって、うつ伏せの状態で倒れている。しかも顔半分は地面に埋もれ、上から布がかぶせてあるのだ。
こ、これはとうとう……人の死体……。
私が凍りついていると、シンバが座席をバシバシと手で叩いてわめく。
「おーい、マサイ! マサイよ!」
その瞬間、地面に倒れたその人がバネのように跳ね起きる。
なるほど彼は生きていた。それどころか普通の人よりピンピンしている。
シンバが彼に手招きし、スワヒリ語で会話する。どうやら彼は、1頭の雄牛とともにセレンゲティを移動中、ここで昼寝をしていたらしい(!)。地面に小さな穴を掘り、そこにしっかり顔まで埋めて。
あっけに取られる乗客をよそに、マサイはシンバから差し出された飲みかけのウォーターボトルを受け取ると、礼を言ってくるりと背を向け去っていく。
「ああ、マサイとは、いったいマサイとはどんな人びとなのだろう?」


ほどなくして。私たちは、とあるマサイの村を訪ねる。
マサイの村には、よそから観光客を受け入れて観光費を収入とする開かれた村があるのだ。
伝統的に家畜のもたらす収入で生計を立ててきた彼らにとって、現代のグローバルなツーリズムに対応するのは大きな決断だったはずで。
車を降りると、わらわらとマサイたちに囲まれる。村の長(族長)に観光費として米ドルを手渡すと、その長男が村を案内してくれる。長男は英語を話す。ほかの人は観光客をじっと見つめて、ぼそぼそと彼らの言葉を交わしている。
まず、マサイの女性たちによる歓迎の歌が始まる。男性たちはそれに合わせてジャンプする。その動きはこれまでに見たことがない。
彼らは空に向かってまっすぐ跳ねる。とても高く。理解しがたいほど垂直に。体重も軽そうだが、それだけではけっして説明がつかないだろう。
マサイに生まれた男たちは戦士として育てられる。彼らは数々の修行や儀礼を経て戦士時代を卒業し、はじめて大人になれるという。
マサイの村は1つの家族を表している。現代では稀に見る一夫多妻で、族長ひとりが複数の妻を持つ。この数は多いケースで15人にも及ぶという。今回訪れた村は大きな規模で90人。ということは……。
「あなたの兄弟姉妹は何人いるの?」
「兄弟が32人、姉妹が49人だよ」
「え?」
つい何度も聞き返したくなるのだが、この村にはひと家族しかいないのだ。ここに並ぶ若者すべてが長男の兄弟姉妹であるという。
族長の長男は私のiPhoneに興味津々だ。
「ぼくがこれでビデオを撮るよ」
言うやいなや、私の手からiPhoneを取り上げる。
「大丈夫、どうやって使うのか知っているんだ」
彼はたっぷり3分間、兄弟姉妹を撮影する。



歌とジャンプが終わる後、私たちは村の中へと招かれる。枝で囲われた壁の中。
向こうから1人の年配女性が近づいてくる。長男の母親らしい。母親は私の手を取り、ほかの女性たちと横一列に並ばせる。
女性たちはーー全員が族長の妻か娘のいずれかになるわけだーー出しぬけに歌い出し、それに合わせて首を動かし、ビーズでできた首飾りをリズムに合わせて上下に揺する。独特の首と肩のコーディネーション。なかなか見よう見まねのできない動き。
歌のあいだ、母親は私の手をにぎったまま。彼女の足がときどきわずかに地面を離れる。地面すれすれにジャンプする。そのたびに、身につけた手製のビーズの首輪や腕輪、耳飾りが宙を舞い、そこからすぐにストンと落ちる。鎖骨のあたりを軽く打つ。
こうして今度は村の中で、観光客はマサイによってもてなされる。

ひととおりの儀式が終わると、族長の息子たちが火起こしの様子を見せてくれる。
マサイは木の枝と枝をこすり合わせて火を起こす。毎日こうして火を起こすのだと彼らは言う。

けれども、なかなか火はつかない。
弟が別の小枝を見つけてやってくる。今度は別の小枝で試す。そのまま数分が経過する。
「マッチを使うことはないのですか?」
私は思わず質問する。
「いや」
するどく返事が突き返される。
「僕らはマッチを使わない」
意志のある声。まるで経典にそう書いてあるとでもいうように。もっともマサイ族は無宗教で、経典というものを持たないのだが。
「……」
火をつける。たったそれだけ、毎日欠かすことのできないことが、どうしてすんなりいかないのか?
私は黙って息子たちを観察する。彼らは細い小枝を両手ではさみ、くるくると回しながら木の板にこすりつづける。
「……」
こうして彼らを眺めていると、私はやがてごくシンプルなひとつのこと、まるで長いこと忘れていた事実を思い出したような気持ちになる。本来、暮らしというのは思いどおりにいかないものだ。火はなかなかついてはくれず、枝と枝をこするうち手には豆ができてしまう。物を洗えば手はかじかんで、屈めた腰は痛くなる。けれども私のように現代の都市部で暮らす人びとは、何気なく、でも実は猛スピードでモノや技術、生活自体を消費するうち、いつの間にかそういう苦労やプロセスを意識の外へ締め出しているのだろう。
バーチャルのある暮らしというのは、その最たるものかもしれない。現代人はスマホを起動するだけで、たとえその場にいなくても、遠く離れたモノやカネ、人や組織を動かすことが可能になる。手のひらのデバイスひとつで通信から移動から、買い物から学習から、さまざまな活動を操ることができるわけだ。でも、じっさいの、リアルな力ははたして……。私たちから技術をとったら、いったい何が残るのだろう?
現代人の暮らしには、強力な魔法の粉があちこち振りかけられている。人間の有能感、万能感を推進してやまないなにか。

つぎは住居に招かれる。マサイの家は、木の枝と牛の糞と灰で固めて作った小屋だ。
「糞」というと面喰らってしまうのだが、じつはまったく無臭である。考えてみれば、牛はただ純粋に草だけを食べるので、これは草が牛の身体をくぐったあとの造形物であるのだとも言えなくない。
そんなわけであらためて、この糞で固められた見事な壁を眺めてみる。
1つの小屋には1人の妻と、その子どもたちが住んでいる。


「ぼくらは5年おきに移動する。家畜がいるからそうしないとだめなんだ」
家畜を育てる草をもとめて、彼らは移動しながら暮らしている。移動した先々でふたたび住居をこしらえながら。
ケニア南部からタンザニアにかけての土地は、マサイランドと呼ばれており、マサイの部族が遊牧しながら暮らしてきた。
彼らはやがて欧州の文明人に「発見」され、土地は国境によって分けられた。マサイランドの使用をめぐり、部族はしばしば政府と衝突を繰り返してきた。現在、マサイは国立公園内で暮らすことを政府から特例的に認められている。
小屋を出ると、村の「学校」に案内される。自分たちで小屋を建て、そこで大人が子どもたちに読み書きや算数、英語を教えているのだ。
「彼女が先生だよ」
見ると、若い女性が(長男の妹にあたるはずだ)こわばった表情を浮かべ、教室の隅にたたずんでいる。幼い子どもが20人強(こちらも長男の兄弟姉妹)、元気よく英語で1から20を数えている。 教室の中心には、訪問者用の寄付箱が置いてあり、子どもたちが20まで言い終わると、満面の笑みでこちらを見る。私は黙って米ドルをその箱に投入する。その瞬間、パチパチと拍手が鳴る。

タンザニア政府は、マサイの子どもや女性たちの教育を支援していると言われている。ここにくる途中にも、マサイのための学校施設を車窓から眺めてきた。政府の運営する学校もマサイの子どもを受け入れている。
彼らはいったいどのようにして外部の環境、その根本的に異なる暮らしに対応していくのだろう。そしてまた受け入れる人たちは。
私はセレンゲティのテントで出会ったマサイのことを考える。これから政府の学校で教師として雇われる、1人のマサイの若者のこと。
たがいに異質な存在が、共に生きるということ。

マニヤラ編
セレンゲティ編
ンゴロンゴロ編
ンゴロンゴロ(1)マサイたち
結び