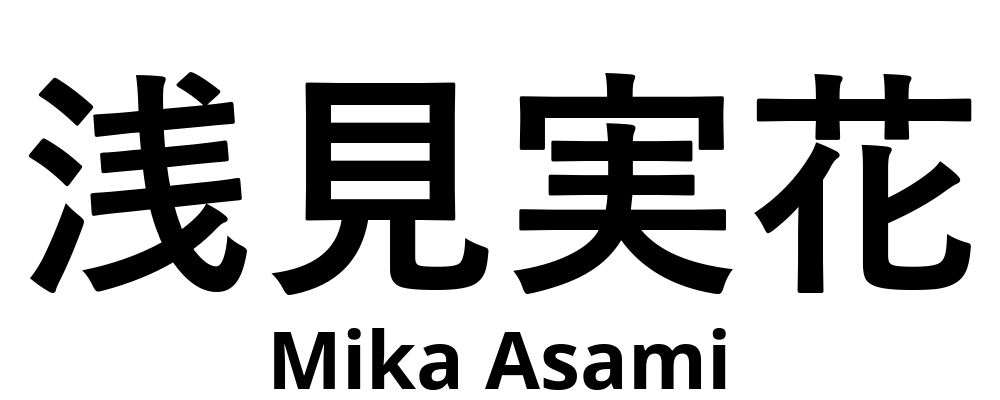アフリカへサファリに行く
セレンゲティ編(7)
アフリカへサファリに行く
セレンゲティ編(7)
テントに泊まる
「え、ここじゃない? ああ、そうか。今日はどこへ行ったんだい?」
「あっちだよ。ここを出て、西へ1マイル進んでごらん」
夕方、平原に設置されたテントの前で、おそらくそんなスワヒリ会話が交わされたはずだ。シンバとテントの係員とのあいだで。
シンバが言うには、今夜泊まる予定のテントが、別の場所へ移動してしまったのだという。動物ではない。宿の話だ。
「移動した?」
「そうだよ。セレンゲティの中だからね。動物が移動するのと同じさ」
そう、ここでは何もかもが移動するのだ。野生動物、とくに肉食動物たちが移動するのにともなって、ヒトはもちろんテントでさえも日々場所を変えて移動する。

やがて、シンバがお目当てのテントを見つける。
テントと言っても、いわゆる素人がキャンプで使用するようなテントではない。中は広い。入ってすぐは寝室で、その奥に簡易式の洗面所とシャワールーム、トイレがある。テント自体はウォータープルーフの厚手の素材で、おそらく二重。出入り口はジッパーを動かして開閉する。床は一面アフリカのカーペットで覆われていて、裸足でも歩けるほどだ。食事をとるのは宿泊客全員で、受付のあるメインのテント。 ここまではまあ問題ない。
1つ問題があるとすればシャワーだ。テントの係員が説明する。
「ここでは水が非常に貴重です。トイレやシャワーの水を使うとき、どうかそのことをご理解ください。シャワーを浴びる3分前に、シャワーを使うと係員に知らせてください。明るい時間をお勧めします。係員がテントの外で待機し、温かいお湯を準備します。なくなったらさらに用意しますので、すぐに声をかけてください」
埃の舞う平原から戻ってくると、頭からつま先までが砂と埃にまみれてしまう。髪の毛は埃を吸ってバサバサになり、白い服は黄色がかった灰色に染まる。そんな日の夕方に、温かいシャワーをたっぷりと浴びることができたなら、どれほど気持ちがいいだろう。けれどもそれは困難な注文だ。だから自分に言い聞かせるよりほかにない。
「シャワーなど浴びずとも人はまず死にはしない」
普段のルーティーンでさえ、ここでは特別な体験になる。

まだ外が明るいので、私は外を散策する。別のテントの横で、係員がどこかで沸かしたバケツのお湯を、ドボドボとパイプの中へ注いでいる。だれかが中でシャワーを浴びているのだ。
中国人の若い女性が、大音声でビデオチャットを楽しんでいる。どうやら旧正月らしい。メインテントの中に入ると、若い中国人の男女が5人、受付前のソファに座ってくつろいでいる。全員とも顔に白いパックを貼ったまま、こちらをジロリと振り返る。
ほかにはスペインの中年の旅行客が4人。中国の若者たちが騒がしく、見るからに不満そうだ。なるほど、たしかに若者たちは興奮している。アフリカのサバンナで旧正月を迎えているので、感動もひとしおなのだと推測できる。けれどもおそらく彼らに悪気はまったくない。ただ気づかないだけで。ガヤガヤと活気に満ちた環境が彼らにとって当たり前であるならば、自分たちが騒がしいこと、それが他人を不快にしているなどと、きっと思いもよらないのだ。
「あの、ちょっと声を落としてもらえますか? あなたがたの声がかなり大きく響いています」
彼らに遠慮はいらないだろう。なにしろ気づいていないのだから……。私はごく率直に、まわりの気持ちを代弁するよう試みる。中国語ではとても勝ち目はなさそうだから、ごく簡単な英語によって。
「あ、わかりました」「オーケー」
若い中国旅行客からあっさりした返事がくる。その中国人の背中の向こうで、スペイン人の女性が1人、手と手を合わせてアリガトウのジェスチャーをする。
メインテントの前で、だれかが焚き火の番をしている。マサイ族の男性だ。薪をくべ、焚き火をつついて火の具合を調整している。私は彼に近づいていく。挨拶して名を名乗り、ひととおり雑談する。
このマサイの若者は教師だった。まずマサイの学校へ行き、のち国立の単科大で教師の資格を取得した。これから政府の学校で教師として働く予定だが、受け入れ先の準備が整っていないので、時期はまだ決まっていない。それまでの期間、彼はこのテントに雇われ働いているらしい。
「ガールフレンドがいるんだ。彼女と結婚するつもりだよ」
いつの間にか結婚の話になったので、私は内心気になっていた質問を投げかける。
「マサイが一夫多妻制だというのは有名だけど、妻たちのあいだでなにか問題が起こることはないの?」
「ないよ。妻たちはとても仲がいいんだ」
「仲がいい?」
「うん。彼女たちはおたがいに愛し合っている」
私はどうしてそうなのだろうと聞いてみる。私たちの世界ではなかなか信じられない事態だ。
「そういうふうに教えられて育つから」
彼の言葉は短くて的確だ。
「教えられる? お父さんやお母さんに?」
「僕らはコミュニティで生きている。幼い頃からそこに入って、コミュニティ・リーダーの話に耳を傾ける。そうやっていろんなことを学んでいくんだ」
「なるほど。それって何歳頃から?」
「1歳と数ヶ月ってところかな」
「そんなに早く?」
「そう」
驚いた。それほどまでに幼い頃から、彼らは自ら属するコミュニティの伝統やならわしを学んでいくのだ。
こんな調子で、私はマサイの若者と焚き火を囲んでおしゃべりをする。彼はとても落ち着いている。まだ若者とは思えないほど。彼はときどき薪をつつく。彼がよく火を手なずけているのが見てとれる。
初めて会ったマサイの若者。自分とはなにもかもが違うこの人と、セレンゲティで焚き火を囲む。それはあまりに日常とかけ離れているはずなのに、どうしてこんなに落ち着くのだろう。ここでは時間がとても静かに過ぎていく。速くもなく、遅くもなく。穏やかな安定したリズムによって。
やがて夜の帳が降りる。あたりを覆う薄闇を火がやさしく照らしている。どこかから冷たい夜風が吹いてくる。アカシヤの木々を抜け、動物たちの身体をかすめてやってくる。それでも火は燃えつづける。じっと静かに耐えるように。火はマサイに見守られ、私の身体はこの火によって暖められる。

マニヤラ編
セレンゲティ編
セレンゲティ(7)テントに泊まる
ンゴロンゴロ編
結び