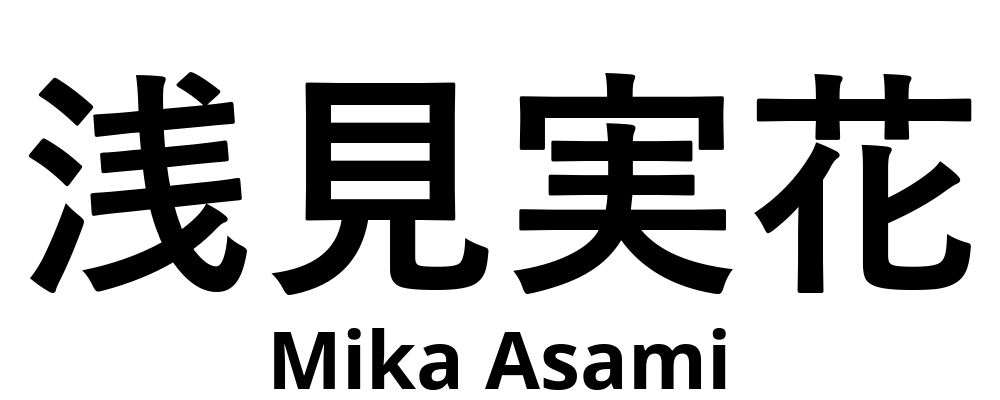インド・バラナシ・巡礼の町
デリー行きの夜行列車
インド・バラナシ・巡礼の町
デリー行きの夜行列車

さて、束の間のバラナシ旅行もそろそろ終わりに近づく。
これから夜行列車に乗って、インドの首都デリーへ向かう。

朝、宿の部屋で荷物をまとめていると、ドアのところへ宿のご主人がやってくる。
「運転手が表にきてる。きみたち、そろそろ行く時間?」
わたしたちはお礼を言って宿泊代の清算をする。
なんだかんだで夫がチップをはずんでいる。
「これはなに?」
宿の主人が受け取った千円札を見つめて言う。
インドのルピーで金額を伝えると、彼はギョロッと目を見開いて、
「これはきみたちにもらった宝物。ちゃんとこのまま取っておく」
宿のご主人にお礼を言う。
「楽しいステイになりました、ありがとうございます。オムライスもよかったですよ」
部屋を出ると、廊下になぜだかインドのご婦人たちが座っている。その列は階段上から階段下まで、廊下を通って外の路地まで続いている。
これはいったい?

思わず宿のご主人に尋ねる。
「この方たちも宿に泊まっているのですか? それとも宿のスタッフですか?」
すると彼は思いもよらない答えをくれる。
「いや、知らないよ。巡礼客。休んでいるだけ」
最後の最後、これから宿を離れるというときに、とうとう彼を心から見直した気分になる。
なんという寛大さ、なんといういい加減さ。
自分の宿の廊下中に見ず知らずのご婦人たちが座り込んで休んでいても、この人はいっこうに構わないというのだから。
これぞインド、これぞヒンズー。
ここでもわたしはヒンズー教ならではの宗教的な寛大さ(神様はたくさんいて、どの神様を信じても構わない。ほかの宗教や信徒にも攻撃的・排他的にならない)、それから彼らの情けある無関心を思い出す(他者がなにをしようと構わない。と同時に、表面的な自己責任論者で終わらず、どこか慈悲をたたえている)。
バラナシの滞在を振り返ると、そんな宗教的姿勢というか、ヒンズー的な生にたいする態度が、この土地の人びとの生活意識全般に染みでているのを感じる。

せっかくバラナシまできたら、もうすこし足を伸ばして「サルナート」へ行くのもおもしろい。
サルナートは、お釈迦様(ブッダ)が初めて説法を説いたという仏教発祥の地だ。ここにはお寺が集積しており、日本式やタイ式のお寺などそれぞれに趣向の異なる寺院を廻ることができるほか、仏教と同じくヒンズー教から枝分かれしたジャイナ教のめずらしい寺院もある。
巡礼ではなく一般的な観光ならば、1日もあればじゅうぶんだろう。
わたしたちは運転手のお兄さんとサナルートを観光した後、夜行列車でデリーへ向かう。



バラナシへくるときは飛行機で1時間半かかったが、ここを夜行列車で戻ると、たっぷり11時間はかかるという。走行距離にしておよそ750キロ。東京・新大阪間の距離より200キロ長い距離だ。途中の駅でどのくらい停車するかは不明だが、単純に計算すると時速68キロになるので、日本の普通の電車のスピードと似たり寄ったりということか。
デリーの旅行会社に予約してもらった切符を見ると、夜9時過ぎにバラナシを出て、朝8時前にデリーに着くと書いてある。
列車には1等席から8等席まであるが、子連れだし荷物もあるしで今回は2等席、エアコン付き。
インド人は階級があるので、たとえば軍人枠や看護師枠など、クラスによって席の枠まで決まっているという。
運転手のお兄さんが夜行列車の駅まで車で送ってくれる。
「ステーション・ネーム・チェンジド。ドント・ウォーリー」
彼は、最近になって駅の名前が変わったけれども心配無用と言うのだが、そんなことを言われると逆に心配になってくる。
本当にこの駅でいいのだろうか?
目の前の駅舎を見ても、ヒンズー語で書かれているためすぐに名前がわからない。
デリーの旅行会社にもらった英語の旅程を見てもVaranasi Stationとしか書かれていない。
念のため、デリーの旅行会社へ携帯から確認の電話を入れる。
はい、もしもし。
ごちゃごちゃ、ごちゃごちゃ……
大丈夫、ここで間違いなさそうだ。

駅構内はとにかく人で溢れ返っている。
インドの夜行列車というのは、列車によってひどい遅延があるのだそうだが(場合によっては数時間)これはもう運の問題と呼ぶしかない。
じっさいに掲示板を見ていると、すでに3〜4時間と出遅れている列車がある。
幸い、わたしたちの乗る電車だけは時間どおりに出るらしい。

プラットフォームは屋外なので、しばらくここの駅舎で待つのがいいと運転手さんが言う。わたしたちが無事に列車に乗りこむところまで付き添ってくれるそうだ。
「どうもありがとうございます」
「オーケー。ミー・ゴー・アウト。ミー・イート」
お兄さんは、ちょっと夕ご飯を食べてくると言って出かけていく。
わたしたちは駅構内で小一時間待つことになる。
時折、例のオレンジ色の衣を纏った巡礼客が元気よく構内に入ってくる。
バラナシでは溌剌とした青年たちが常にああして裸足で走り回っていたが、彼らはなんとあのテンションを保ったまま何百キロも離れた農村へ帰って行くのだと、ガイドのラジさんが言っていた。
多くの巡礼客は地方の町や村から来た農家で、人によってはひと月もかけて徒歩によってバラナシへ、人生の一大イベントとして巡礼へやってくるという。

いつの間にか運転手のお兄さんが戻ってきた。
構内にヒンズー語のアナウンスが響いている。お兄さんは耳に手をあて、放送を注意深く聞いている。ヒンズー語のアナウンスのあと、英語が流れてきはしないかと淡い期待を抱いてしまうが、放送はそこでプツリと切れてしまう。
お兄さんによれば、プラットフォームが急遽変更になったとのこと。
わたしは電光掲示板に目をやるが、その変更はまったく反映される様子がない。
ヒンズー語が聞き取れなければ、プラットフォームもわからないのだ。

屋外のプラットフォームのベンチには、人びとが疲れた身体を横たえている。彼らはパッと見、旅人なのか物乞いなのかよくわからない。
そして列車がやってくる。デリー行きの夜行列車だ。
運転手さんにチップを手渡すと、お兄さんはもっと、もっと、と仕草する。たしかに、たしかに。彼が付き添ってくれなければ、プラットフォームの変更もわからなかったわけだから、きっと多いに慌てることになっただろう。
わたしたちはあらためて感謝を示し、チップの額を多めに払う。お兄さんはニッコリ笑い、わたしたちに手を振っている。
「シー・ユー・アゲイン」


とにかくただの列車ではない。だいぶ古めかしいものの、正真正銘の夜行列車。
いざ車体を前にすると、旅の情緒がぐいぐいと高まってくる。

ドッ、ドッ、ドッ、ドッ……
席に着くなり、いよいよ列車が動き出す。その動きはゴツゴツとしてぎこちないが、とにかく力はこもっているのが伝わってくる。
わたしたち5名の席は、向かい合った2段ベッドの2セット(4名分)と、見ず知らずのだれかとの共有となる2段ベッドの2段目(1名分)。
2段ベッドの2セットは、カーテンを下ろしてしまえば、個室のようなプライベート空間になる。ここにわたしと子どもたちが陣取って、共有ベッドの2段目には夫が眠ることになる。
子どもたちは張り切って自分のベッドを作っている。
夫の下は、賢そうな30代のインド人男性で、ブランケットをかぶりながらカーテンをさささと引く。

やがて車掌がやってくる。チケットを確認すると、夕食は必要かと尋ねてくる。
いいえ、もう済ませたので大丈夫です、ありがとうございます。
わたしは早速、車両後尾のトイレをチェックしに行く。
そもそも期待はもたないようにしているが、そういう意味では期待のとおり。
バラナシの旅行中は、常にトイレットペーパーを持ち歩いて移動した。あきらかに下水道の管が弱そうな旧市街では、使用済みのペーパーは備え付けのゴミ箱に捨てるとか、ペーパーではなく備え付けのミニシャワーで洗い流してきたのだが(これは毎回シャワーを浴びるようなものなので、拭うよりも結果としては清潔だ)、ここにはなんとゴミ箱もミニシャワーも見当たらない。
代わりにあるのは小さな蛇口と手桶のセット。これはもう覚悟を決めて、手桶の中に水を溜め、己の手により汚れを清めるやりかたに従うほかなさそうだ。
座席に戻って子どもたちを寝かしつけ、すでに暗くなってしまった窓の外を眺めながら、買っておいたビール缶に手を伸ばす。
・・・・・・
ガターン、ガターン、ガターン、ガターン、
列車はひどい騒音で狂ったように突き進む。計算上けっして速くないはずなのに、この騒ぎでは全速前進、まるでなにかの記録に挑んでいるかのような心象を抱かせる。しかもますます加速しているように感じられるが、シートベルトやエアーバッグの安全装置があるはずもなく、乗客は文字どおりボロボロの寝台列車にすべてを任せることしかできない。
だんだん夜は深くなり、アルコールがゆっくりと身体を循環する。高速で移動する2段ベッドに横たわり、いつの間にかウトウトと眠りにつく。
・・・・・・
ドッカーン、ドッカーン、ドッカーン、ドッカーン、
夜中にふと目を覚ます。停車駅の間隔が果てしなく広がったのか、列車はもはやとんでもないスピードに達したように感じられる。
ほかの人を起こさないよう、そっと窓のカーテンをめくり上げる。
真っ暗で、なにも見えない。
列車の車輪がもの凄い摩擦でレールをこすりつけている。
いま、いったいどんな土地にいるのか自分には見当もつかない。なにしろ列車がこの騒ぎなので、だれか起きる人もいるだろうと廊下を覗くが、この車両はどこもかしこも寝静まり、人の気配が感じられない。
しかたなく、隣のベッドの末息子を眺めてみる。彼はこの轟音の中、スヤスヤと天使のように眠っている。

・・・・・・
気がつくと、窓の外が白んでいる。
朝の5時半。
窓の外には、未舗装の土の道路と畑と荒地が広がっている。
こんなに朝早いのに、もう土の上をどこかに向かって自転車をこぐ人がぽつん、ぽつんと目に入る。彼らはしばらく先の小さな村を目指して進んでいるのだろう。
おーい、オハヨー!
わたしたちを乗せた列車は、猛スピードで彼らをビュンビュン追い抜いていく。
窓の向こうに民家も見える。住居というよりこれらは小さな掘っ建て小屋だ。
風雨をしのぐための屋根や壁があり、人が出入りするための扉があって、換気や外を眺めるための窓がある。
水道はどこまで発達しているだろうか。電気はおそらく付いている。そこではきっと慌ただしい朝の支度があり、炊事洗濯、仕事に出かける人がいて、学校に出かける子どもたちがいるだろう。人びとは朝の挨拶を交わし、朝ごはんを済ませたら、それぞれの1日をスタートさせる。

「チャーイ、チャイ、チャイ、チャイ、チャイ、チャイ……」
突然、車内にチャイ売りのおじさんの低い声が響く。大きな水筒を肩にかけ、朝のお茶、チャイを売って歩いているのだ。この光景もまたインドの列車ならではだろう。まわりにチャイを頼む人がいないのか、おじさんは狭い通路をサッサと通り過ぎてしまう。
「チャーイ、チャイ、チャイ、チャイ、チャイ、チャイ……」
列車の騒音におじさんの声が掻き消される。
夫と2段ベッドを共有していたビジネスマンらしきインド人はすでにどこかへ行ってしまった。彼の使った毛布が無造作にベッドの上に丸められ、空っぽの食事トレーが台の上に置かれている。本当に、いろんな人がやって来て、いろんな人が去っていく。
いま、となりの線路でわたしたちと反対へ向かう列車がすれ違う。
こちらと同じで、向こうもこちらをじっと見つめる。
わたしはカメラのファインダーから彼らを覗く。カシャカシャとシャッターを切る。なかなかそれをうまく捉えることができないけれども。


シュシューッ、シュシューッ、シュシューッ、
ひと晩の荷物をリュックへしまっていると、列車はもう終着駅のプラットフォームに近づいている。
キーッ、キーッ、キーッ、キーッ、
終わりというのはあっけない。それは突然やって来る。後ろからポンと肩を叩かれるみたいに。
プシューーーーーーーーーーーーーー、
いま、巡礼の小さな町・バラナシが去っていき、巨大な首都で国際都市・デリーがズンと立ちはだかる。
急速に祈りが薄れ、精神が遠のき彼方に流れ、わたしたちは夢から覚める。
ガタン。
そしてすべてが変わってしまう。
わたしたちは列車を降りる。
ガヤ、ガヤ、ガヤ、ガヤ…… 喧騒、雑踏、忙しない駅の風景。

列車を降りた人びとはそれぞれの場所へ、それぞれの方角へ向かって荷物を転がし、ゆっくりと進んでいく。
(おわり)
<参考文献>
森本達雄『ヒンドゥー教 インドの聖と俗』(中公新書)
河田清史『ラーマーヤナ インド古典物語(上)(下)』(第三文明社)
冬野花『インド人の頭ん中』(中経の文庫)