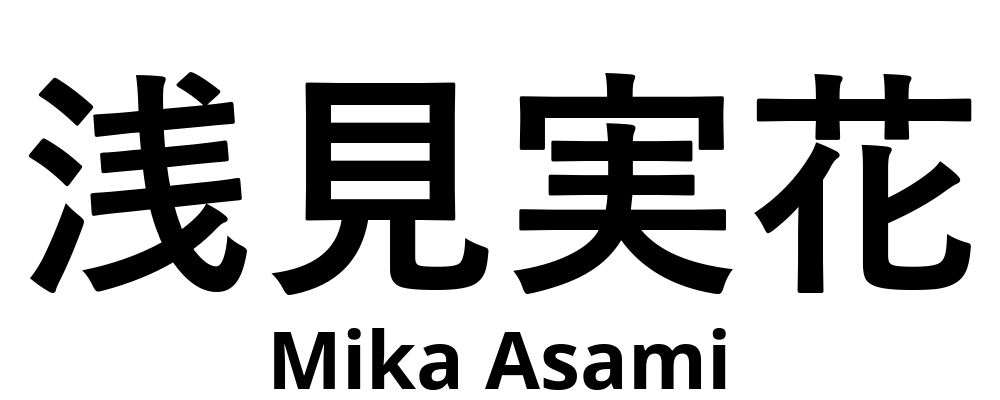インド・バラナシ・巡礼の町
カーシー・ヴィシュヴァナート寺院
インド・バラナシ・巡礼の町
カーシー・ヴィシュヴァナート寺院

京都のゴールデン・テンプルが金閣寺なら、バラナシのそれはカーシー・ヴィシュヴァナート寺院だ。
ガイドブックの写真を見ると、金箔を施されたドームがピカピカと輝いている。

中での写真は厳禁だ。カメラはおろか携帯電話の持ち込みも許されない。
外国人観光客はパスポートと現金(お布施)のみを携えて、警察による身元チェックを受ける。
末っ子が疲れているのでいったんみんなで宿に戻り、末っ子に休息させる。
寺院へは二手に分かれて交代で行くことにする。
まずわたしが上の双子を連れて行き、そのあとに末っ子と夫が寺院へ行く。
「はい、これパスポート。行ってらっしゃい」
夫からパスポートを手渡され、わたしと双子は寺院へ向かう。宿から徒歩でわずか数分 。
なんだかんだで便利な宿だ。

オレンジ色の衣を纏ったシヴァ神ファンたちは、手の中に小さな壺と、お供え用のマリーゴールドを持っている。そこら中の商店でこうした巡礼グッズが売られている。

「ゴールデン・テンプルはこちら」
ほどなくして寺院への看板が見えてくる。
人混みが尋常ではない。まさにこの混乱がゴールデン・テンプルのありかを示している。

いったいどこから行列に並ぶのだろう。
近くの店のおじさんが話しかけてくる。
「外国人観光客はこの行列じゃない。もっと先のゲートへ行け。そこでパスポートを見せるんだ。カメラや貴重品はここに置いていけ。鍵付きのロッカーがあるから使っていい」
なるほど、この人は貴重品ロッカーを売る商人だ。
「貴重品はありません。ありがとう」
オレンジ色の巡礼団に揉まれながらずんずん先へ進んでいくと、目の前にセキュリティゲートが現れる。
ほんらいは金属に反応すると警報が鳴る仕組みだが、見るとなぜだかだれでも人が通るたびに「ピー!ピー!」と鳴っていて、しかもだれも呼び止められない。だったらなぜゲートがあるのと不思議になるが、そう思う間にも数珠のようにビッシリ並んだ巡礼客が寺院のほうへ押し寄せる。
ゲートの先には外国人観光客用の手続き所があり、警察官がパスポートを見て訪問者の名前や番号を記帳している。
ここでもやはり「日本人≒仏教徒=ヒンズー教徒の仲間うち」という例の図式が作用して、日本人はあれこれと質問を受けることなくスムーズに寺院に入れてもらえるらしい。
早速わたしは日本国パスポートを開いて見せるが、そこには堂々別の人、夫の写真が載っている。
ありゃりゃりゃ。
宿を出るときパスポートを取り違えたのだ。
けれども記帳役の警官はびくともしない。表情ひとつ変えることなく、機械のように夫の名前をボロボロの帳面に写し取る。
「……」
顔写真を見ないなら、なんのためのIDチェックなのだろう。警官はいまだペンを休ませない。
「……」
ま、いっか!
わたしと双子は裸足になる。日本のお寺やモスクでも靴を脱がねばならないが、ヒンズー寺院は靴下も脱ぐ。聖水があちこちに撒き散らされて、石の床までびしょびしょだ。
さてこの寺院、建立の年は不明だが、12世紀にはイスラム教に破壊された歴史を持つ。その後も時代の趨勢によって破壊と再建を繰り返し、いまの姿に落ち着いたのは18世紀のマラーター王国時代。
イスラム教のムガル帝国によってモスクにされたこの場所を、マラーター王国の支配者がふたたびヒンズー寺院に造り変えたと言われている。
どっしりした門をくぐると、白い本堂がうず高くそびえている。てっぺんには黄金のドームがキラキラと輝いている。これは19世紀にシーク王国の創設者が寄付した1トンの金なのだそう。一般的にシーク教の人びとはビジネスに長けていてお金持ちが多いと言われる。彼らは収入から一定の割合を寄付する教えを持つことでも有名だ。
後ろのほうから巡礼客が次から次へと入ってくるので、入り口付近は立ち止まることができない。
出入り口には警官が立っていて、「こっちへ行きなさい!」「そっちに行ってはダメ!」などと大声を張り上げている。
敷地は思ったよりずっと狭い。もしだれもいなければ、ひと回り歩くのに2分もかからないだろう。
ふと目の前のお寺の鐘をガラン、ガランと鳴らしてみる。
この寺院には1日3千人以上の巡礼客が訪れると言われている。
たしかに人でギュウギュウなのだが、この敷地の雰囲気は街の中のガヤガヤ感とはあきらかに様相が異なっている。
巡礼者の感きわまった静かな熱狂。彼らの至福と畏怖の念が体中からみなぎっている。これぞ信仰、これぞ宗教。
数メートル先の中庭に、合掌しながら涙を流し、立ち尽くす女性がいる。彼女は本堂を拝みながら、顔を濡らして祈りを捧げる。
わたしたちの行列はいよいよ本堂に収められた例の「リンガ 」(→参照:火葬場とその周辺)、それもインドの主要な寺院12か所に限られるという特別な「光のリンガ」を参拝する。
信者たちは「光のリンガ」の上から注がれるガンガーの聖水を小さな持参の壺に収め、大事に家まで持ち帰るのだ。

Photo: House of God
混み合った本堂を出て中庭に出ると、まわりの塀を猿たちが散歩している。
猿というのはヒンズー教にも馴染みが深い。ヒンズー教徒のだれもが親しむ『ラーマーヤナ』(古代インドの叙情詩)は、人間の王子「ラーマ」(大神ヴィシュヌの生まれ変わり)が妻の王女「シータ」を奪った魔王をうち破り、悪魔たちから全世界を解放する物語であるのだが、この戦いで強力な援軍となるのが猿の大軍なのだった。この猿たちの大将はハニューマン(風の神の生まれ変わり)という黒い顔の大猿で、いまでも黒い顔をした猿の種は猿の中の貴族と呼ばれ、インドの森に生き残っているという。

Hanuman langur (Grey langur)
わたしたちはしばし端のベンチに座る。
まわりには日本人はおろか外国人がほとんどいない。西洋人、おそらくはスペインかイタリアのカップルが遠くに見える程度で、聞こえてくるのはヒンズー語のおしゃべり声や巡礼客のどよめき、入り口付近の鐘の音、それから時折警笛の音。
こうして寺院の片隅に腰をかけ、お堂のまわりで祈りを捧げる人びとや、感動のあまり打ちひしがれる人びと、地べたで談笑する人びと、瓦礫の上の猿たちをボンヤリと眺めていると、なにやら頭の上のほうから特別な旋律が降り注いでくるかのような妙な感覚に襲われる。まるで空間に穴が開き、そこから七色の鐘の音が漏れ聞こえてくるような。
本堂となりの小部屋に入ってみると、バラモン(僧侶)がまた別のリンガの前に立っていて、わたしを見るなり手の中のなにかを指でこそげ取り、こちらの眉間のわずか上、額の真ん中にそれをこすりつけてくる。「ティカ」と呼ばれる、インドの女性がつけている例の赤い斑点だ。このありさまをつぶさに見ていた双子のふたりは、いちもくさんに中庭のほうへ逃げていく。
年老いたバラモンはなにも言わず、部屋の中をウロウロすると、またどこかへ行ってしまう。
こうしてわたしと双子の子どもは、インドのメジャーな信仰が民に与える計り知れない力とその源に圧倒されつつ、やっとのことで帰路につく。
長い長い行列を逆走し、巡礼客のあいだを縫って、おそらくは寺院警備の警官たちの休憩所を通り過ぎ、異臭のひどいゴミ捨て場を足早に、宿に戻る。


カーシー・ヴィシュヴァナート寺院
食べもののこと、河畔のテラス
デリー行きの夜行列車