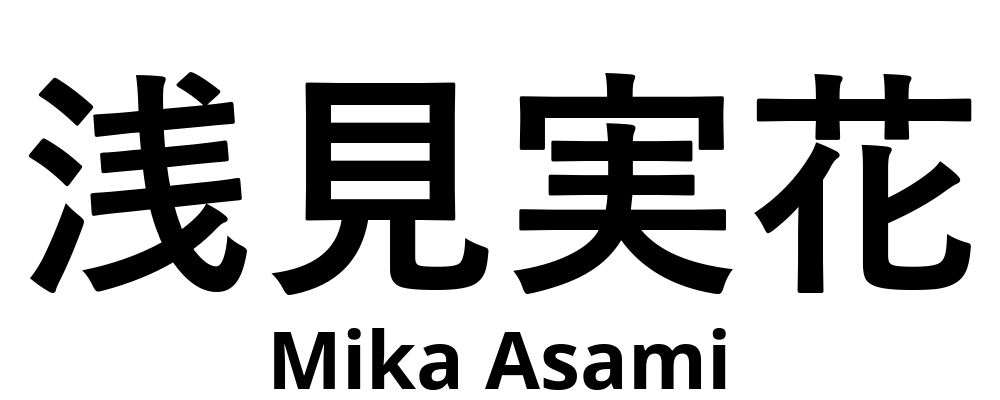1本につながった太くて黒い眉。三つ編みのアップヘアに、華やかなヘッドピース。ボリューム感たっぷりの民族衣装……。
その名前を知らずとも、なんとなく既視感がないだろうか。
フリーダ・カーロ(1907-1954)
彼女は波乱万丈な人生を生きながら、革新的な自画像を数多くのこしたメキシコの女性芸術家で、その影響は絵画のみにとどまらず、民族芸術やファッション、デザインなど多岐にわたると言われている。
そんな彼女の特別展がV&A美術館(※)で大大的に開かれたので、さっそく足を運んだ。
(※装飾芸術・デザインのコレクションで世界一の規模をほこるヴィクトリア・アンド・アルバート博物館)
公式サイト “Frida Kahlo – Making Her Self Up”
この展示では、2004年にフリーダの自宅「青の家」から見つかった数々の私的な持ちもの(衣装やアクセサリー、写真や手紙など)がまとめて公開されており、こうした私的な品物から彼女のライフ・ストーリーを解釈しようという試みになっている。

***
ところでこのフリーダ・カーロという人は、一般的にどう語られてきた人なのか?
I paint self-portraits because I am so often alone, because I am the person I know best.
自画像を描くのは私がいつも孤独だから、そして私のもっともよく知る人が自分自身だからです。
興味を持った私は、事前に彼女にかんする本や記事をいくつか読んでみた。
そして知れば知るほど、彼女に引き込まれていった。
彼女の描く自画像は、きわめて個人的で内的なものでありながら、しばしば苦痛をともなった現実(物理的、精神的に)をどこまでも冷静に、そして果敢に描き切ろうとしている。彼女の絵を眺めていると、その様子がありありと伝わってくるようだった。
My painting carries with it the message of pain……Painting completed my life.
私の絵は痛みのメッセージを含んでいます…….絵を描くことで私の人生は完成するのです。I never paint dreams or nightmares. I paint my own reality.
私は夢や悪夢について描いたことはありません。自分のリアリティを描いているのです。
彼女の人生は、当初から苦痛や不運と切っても切り離せないものだった。
6歳のときにポリオに感染。後遺症で彼女の右脚はいちじるしく痩せ細ってしまう。これをきっかけに彼女はロング・スカートや長ズボンでその脚を覆い隠すようになっていく。
さらに18歳のとき、乗車していたバスが路面電車に衝突。大怪我を負う。彼女の身体のあちこちに瓦礫が刺さり、背骨、骨盤、脚などを損傷する。この傷は生涯にわたって彼女に激しい痛みをもたらし、その治療に計22回の手術を要するほど致命的なものだった。またこの怪我は、彼女を妊娠困難な身体にもした。
こうした激しい後遺症や妊娠の挫折や心の葛藤は、生涯を通じて頻繁に彼女の絵画に表現されているーーーe.g. 亀裂の入った大地に立ち尽くす、身体中に釘の刺さった殉教者のような自画像:”In The Broken Column”の絵画。
I am not sick. I am broken. But I am happy to be alive as long as I can paint.私は病気ではありません、私は壊れているのです。けれども絵を描いていられる限り、幸せに生きられます。
22歳になったフリーダは、当時メキシコでもっとも成功していた芸術家のひとりで(公共建築物などに巨大な壁画をのこす)20歳年上のディエゴと結婚する。ディエゴは巨大で体重過多、しかも強烈な性格の持ち主であるいっぽう、フリーダは小さく華奢で、脆弱だった。この結婚を好ましく思わなかったフリーダの両親は「ゾウと鳩の結婚」と評したと言われている。ふたりは外見も描く絵の趣向も対照的であったものの、芸術への情熱と政治的な信条では思いを強く共にしていた。ディエゴは彼女の作品を讃え、辛い痛みの中でも絵を描き続けるよう、彼女を励まし続けた。
しかし、ディエゴの度重なる浮気とのちのフリーダの浮気によって、ふたりの結婚生活は破綻する。
別離のあいだ、フリーダはひどく落ち込み、その経験もまた絵画に注ぎ込まれていったーーーe.g. 男性用のダークスーツに身を包み、ハサミを持って椅子に座り、まるで囚人のように髪を切り落とした姿の自画像:”Self-portrait with Cropped Hair”の絵画。ディエゴはのちに、この時期のフリーダの作品が皮肉にも素晴らしい出来栄えになったと評している。
There have been two great accidents in my life. One was the trolley, and the other was Diego. Diego was by far the worst.私の人生で大きな事故が2つありました。1つは路面電車で、もう1つはディエゴです。ディエゴのほうが遥かにひどいものでしたが。
離婚して1年後、それでもふたりは芸術と政治的改革を追求するため、互いの存在が必要であるという思いに至り、再婚を果たす。
彼らはフリーダの生家であった「青の家」をより心地よい空間へ改装し、そこで以前より平和な生活を送るようになる。緑豊かな庭には、ペットの鶏や鳩、魚、犬、小鹿、オウムも暮らした。
フリーダの絵画にはディエゴも繰り返し登場しているーーーeg. 宇宙と大地にフリーダが抱かれ、そのフリーダが額に賢者の目を持つ赤ん坊のディエゴを抱いている自画像:“The Love Embrace of the Universe, the Earth (Mexico), Myself, Diego and Senor Xolotl”の絵画。
Diego was everything; my child, my lover, my universe.
ディエゴはすべてでした;私の息子で、私の愛する人で、私の宇宙。
それでも彼女はベッドの上で絵を描き続け、生涯を通じて150点を超える多くの作品を生み出した。最後は治りかけた肺炎が再発しそれが命取りとなった。 47歳の若さだった。
I hope the leaving is joyful. And I hope never to return.
去ることはよろこびなのだと思っています。そしてもう二度と戻ってきたくありません。
今回の展示 “Frida Kahlo – Making Her Self Up” は6月中旬のスタートで、5月の終わり頃から告知のニュースやイベントを見かけるたびに「ぜひ行きたい」と思っていたら、予約開始早々に月内の予約が売り切れとなっていた。
会場もかなり混み合っていて、作品の前で人と人とがなんとなく譲り合うような雰囲気。訪問者の大半は女性で、若者からシニアまで年代はさまざま、みな熱心に作品を鑑賞していた。
会場をひと回りして、ここにある大小さまざまな品物と、彼女の人生との密接な結びつきを感じ取れたように思う。
たとえば、彼女が背骨の痛みを和らげるため装着していたコルセット。そこに描かれた、生まれなかった彼女の胎児の絵。彼女の縮んだ脚をかばうためヒールを高く構築し、足首の部分を細く絞った右足の靴。真っ赤なレザーとシルクの生地をあしらったブーツ付きのおしゃれな義足。オレンジの木と動物たちでいっぱいの「青の家」の庭、その設計スケッチ。彼女が大好きだった父親の写真と肖像画。がっしりとしたディエゴの肩に頭をもたせかける華奢なフリーダ、ふたりの写真。メキシコの鮮やかでエキゾチックな民族衣装の集合的ディスプレイ……。そんなひとつひとつのアイテムに、彼女の背負った運命と苦悩、それに対する彼女の絶望と抵抗がべったりと乗り移り、複雑にからみあう影と光を投げかけているような気がして。
展示の出口には、いつものようにショップが併設されていたが、これだけ多くの女性たちが熱心に買い物している展示もめずらしかったと思う。本当にすごい力を持った芸術家なのだろう。とりわけ女性に。
1980年代のフェミニズム台頭と、それにともなう女性芸術家にたいする評価の見直しによって、一気に現代芸術のトップに躍り出たフリーダ・カーロという女性。のちに彼女の顔がプリントされた製品が世界中に溢れかえり、彼女のファッションは1つの確立されたアイコンと化した。彼女のスタイルは現代の著名なデザイナーやセレブリティにも多大な影響を与えたと言われている。
いったいフリーダ自身、こんな未来を思い描いただろうか。
この展示のオープン前、スポンサーである不動産開発企業がロンドンの超高級エリアで「フリーダ・カーロ」にちなんだイベントを催して、その区画を華やかに盛り上げていた。エクストラヴァガントーーーひとことで表すならそういうことだ。
もはやフリーダ自身の生とは遠くかけ離れたロンドンのポッシュな地区、彼女の苦悩の「く」の字も見えない場所で、「フリーダ・カーロ」ブランドがかつてないほど煌びやかに、文字どおり「花」開く。彼女の絵画は数億円で取引される。
展示の中で、ディエゴとフリーダが何かを描くフィルムがあり(彼らはコミュニストだったわけだが)、そこでだれかが声高に叫んでいた。
「アートはひと握りの大金持ちのためにあるのではない! すべての人のためにあるのだ!」
なんて皮肉的なんだろう。
フリーダのニックネームでもあった「花」でいっぱいのベルグレービア地区を通りかかったいつかの日を思い出し、私は一瞬そう思った。
けれどもすぐに、思い直した。世の中のシステムは多分そういうものなのだ。だれがどう言おうと、そういうふうにできているのだ、と。そしてそこに、つまり既存の支配的なシステムや枠組みにNO!を突きつける人びとが、芸術家と呼ばれる人たちなんだろう。きっと。