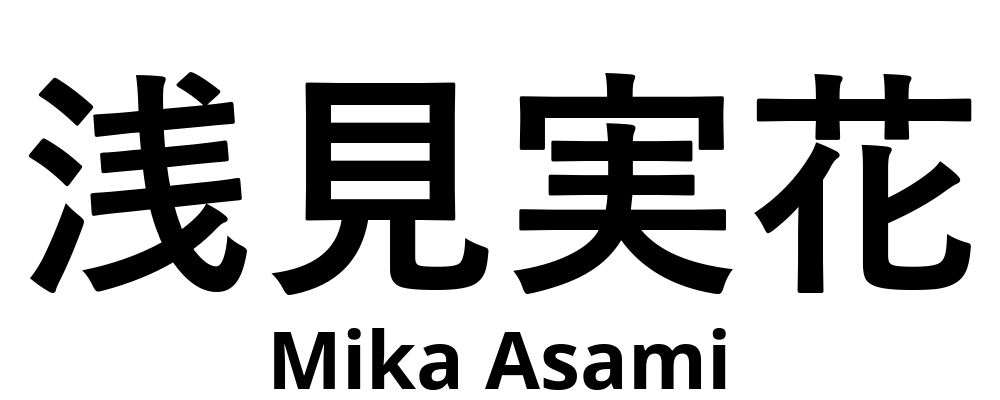うちにオカメインコがやってきたのは3週間前のことだった。
ブリーダーへ予約していた「シナモンパイド」と呼ばれる種で、うす黄色の綺麗な羽に覆われた、ほっぺのところがオレンジ色の、生後2ヶ月の男の子だ。
☆
ブリーダーのOさんのお宅では、数あるオカメインコの中から「ほうら、この子だよ」というふうにその幼鳥を紹介された。
「おお、いよいよこの子がうちに……」
Oさんがひょいと掴んだ小さな鳥を見ていると、ひさしぶりに胸が高鳴り、子どもの頃に戻ったような気分になったーーー小学生のとき、母親がカナリヤのつがいを飼っていて、ちょうどこの小鳥のように黄色い(あれはさらに濃い黄色の)羽をもっていた。手乗りでこそなかったが、カナリヤは毎朝決まって歌をうたい、雌のほうはしぜんに雛まで産んだのだった。
さっそくOさんの奥さんが、携帯用の虫かごにその子を「さあ」と移してくれる。子どもたちはこの幼鳥に釘付けだった。
私はOさんへいくらかアドバイスをもとめた。
「餌はセキセイインコ用のものを与えればいいんでしょうか?」
「そうだよ。セキセイインコ用の餌、それからここのカルシウム、あげるから。あとお水な」
「このカルシウムって手作りですよね? なくなったらどこで手に入れればいいでしょう?」
「そうだなー、そしたらまた取りにおいで」
「え? いいんですか?」
「いいよ、やる、やる」
Oさんは一見かなり強面の、いかにも筋金入りという印象なのだが、心根はきっと優しい人なのだと思う。
振り返ると、おっとりした奥さんが虫かごの冷たい床に、木の屑を敷きつめてくれていた。
「このタネも入れておくね。うちのオカメちゃんはこれが大好き。帰り道でお腹がすいたら食べられるでしょ」
かごの中の小鳥は、ときどき「よいしょ」と肩を持ち上げ、両羽を広げてみせた。その姿はまるで小さなドラゴンの赤ちゃんのようにも見えるのだった。
私はOさんにお願いし、さらにアドバイスをもらったーーー体調がわるいときは、丸くなって眠りがちになること。それが起きたら、すぐに小さなかごに移して、三面にタオルや毛布をかけてやって温めること。そうすれば時間とともに元気になること。餌は決まった餌しか与えないこと。あたらしい環境で餌を食べない子もいるが、お腹がすけばかならず食べてくれること……。
それにしてもオカメインコは見れば見るほどうつくしく、愛らしくて気品があった。うす黄色のすべすべした羽、ふわふわのトサカ、長い尾、オレンジ色の丸いほっぺ。目は潤んだ漆黒で、まぶたもちゃんと付いている。
オカメはまた臆病さでも有名で、緊張するとトサカがピンと立つと言われる。さっそくトサカに注目すると、それはもうまっすぐ天へ伸びていた。
私たちはOさん夫妻にお礼を言って、帰路についた。
帰りの車内で、小鳥は娘の膝の上で大事そうに抱えられ、ときどき名前を呼びかけられた。みんなで話して、名前は「マロ」と決まっていた。
「マロ〜、マロ〜」と子どもがさかんに呼んだ。
「マロ〜、だいじょうぶ? こわくない?」
かごの中でマロはぜんぜん鳴きもせず、トサカを立てたままジッと動かなかった。
☆
自宅に用意してあったオカメ専用ケージの中で、マロはひどく緊張していた。
「マロ、マロ」と呼びかけられても、もっとも離れたかごの隅へサッと移動してしまう。それを見て、頭のくるくる回る長男がもっともらしいことを言っていた。
「ね、考えてもみてよ。生まれたときから仲間たちと暮らしていたのに、ある日突然知らない人がやってきて、誘拐されるようなもんなんだよ。そりゃあ大変だろうよ、マロも」
その日、マロは何も食べず、私たちは気を揉んだ。幼鳥が体重を落としすぎると、命の危険があるためだ。
けれども翌日ケージをみると、餌の入ったプラスティック容器のカバーの上で、ツルツルとスケートのように足を滑らせて奮闘しているマロを見つけた。どうやら、プラスティックが透明なので、カバーの上に乗っては餌に到達できず、困っているのらしかった。
「あららら(笑)」
気がついた私と娘で、プラスティックの餌入れを陶器のものに置きかえた。以前引き出物でもらったル・クルーゼの小さなお皿は、マロのほおのオレンジにぴったりの色だった。マロはさっそく陶器に近づき、首を伸ばして夢中で餌をつつき始めた。
「マロ、お腹が空いていたんだね」
心配そうに見ていた娘も、これでやっと安堵した。
☆
それでもマロは、なかなか人を寄せつけてくれなかった。
私たちは振られるたびに長男の発言を思い出し、「まあ、無理もないよ」「まだ2ヶ月の子どもだしね」と、はやる気持ちを落ち着けた。子どもたちはマロがすぐにでも手乗りになるのを期待していた。自分の手や肩に鳥を乗せ、1日に1回は放鳥してやる体験も心待ちにしていたようだった。しかし彼らはほんものの生きものを前にして、待つということを学ばなければならなかった。私たちはマロにそっぽを向かれたり、壁側に向き直られたり、隅のほうに移動されたりしながらも、遠目から「マロ〜、マロ〜」と朗らかに彼の名前を呼びつづけた。
☆
4日目に変化があった。
朝、静かなときに私が名前を呼びかけながらニコニコと近寄ると、マロは突然それまで見せなかった行動にうって出た。
金網にくちばしと両足を引っかけて、私のほうへ網づたいにゆっくり移動してくるのである。その動作は鳥にしてはのろのろとしたもので、恐る恐る、迷いながら近づいてくるようでもあった。
そのさまを見つめていると、私は初めてこの鳥に、なにか切実なものを求められているような気になった。
「うん、おいで。こっちだよ」
私はもう扉をあけて、巨大な手をケージの中へ差し出していた。自分でも、なにが起きているのかいまひとつわからなかったが、いずれにせよ、自分はそれを受け止めなくてはならないし、いまがそのときなのだと思った。
そうしてマロがおっかなびっくり網を渡り、黙って手のひらに乗ったとき、鳥は私にとって特別な鳥になったのだった。
☆
それからマロは、子どもたちともどんどん距離をちぢめていった。
迷ったあげく、ケージはLDKに置かれることになったので、飛び交う家族の会話にも、マロはまるで自分が参加しているかのように、しきりに耳をそばだてた。食事中は、みんながものを食べているので、マロもいっしょに陶器に首をつっこんで、餌をパチパチついばんだ。
マロはオカメの雄らしく、カナリヤとまではいかないまでも、毎日元気にピィピィ、ピィピィさえずるようになっていた。ときにそれはうるさいほどで、私たちを苦笑させた。「マロ」と呼ぶと、「ピィ」と反応が返ってくる。それからまた「マロ」と言うと、もう一度「ピィ」とくる。タイミングも絶妙だった。
それからときどき、甘えるように頭をかしげて見つめてくる。オカメには一般的に掻いてあげるとよろこぶ場所がほっぺの下にあるのだが、マロにとってはいまひとつと見え、そこを撫でるとまるで人間がぶつぶつ文句を言うように、もぞもぞとくちばしを小刻みに震わせた。むしろ彼のスポットは、よく言われるほっぺの丸の下でなく、背中側の首の付け根であることを突き止めたのは娘である。以降、マロは甘えるときに頭を下げ、さすってくれと私たちにお願いするようになった。
☆
慣れてくると、放鳥も1日1回行った。
長男と長女がそろって下校してくると、マロをかごから取り出して、部屋の中を飛ばせてあげる。最初はマロもまちがえて天井に激突したが、さいわいなんの怪我もなく、じきに空間を把握した。
放鳥のあいだ、ふたごは協力して床に敷いた新聞紙を取りかえたり、ケースの一部を洗ってやる。マロは部屋を飛び回ったり、そうかと思うとのこのこと床を歩いたり、子どもの手や肩に乗ったりして、やっぱり最後は首の付け根も掻いてもらう。掻いてあげると気持ちがいいのか、目を閉じてウットリと夢心地の表情を見せてくれる。
☆
マロがきて、あっという間に3週間が過ぎた。
オカメインコの寿命は長く、一般的に10年から15年以上と言われている。
だからこれは青天の霹靂で、まったく予想もしていないことだった。
マロは死んでしまった。
☆
「なんだか急に元気ないな」「どうしたんだろう?」「今日は丸くなって眠ってばかりいる……」
そう気づいて、ブリーダーのOさんに言われたように、かごの三面タオルを巻いて温めてやった。軽井沢は寒いので、冬季のLDKのエアコンはつけっぱなしにせざるをえないが、それでも温度を高めにし、けっして寒さで弱らないようにと気をつけた。
それでも翌日、マロは顔をうしろの羽に埋め、ますます眠りがちになった。
ときどき餌を食べるものの、なお眠ってばかりいるマロを見ていよいよ心配になった私は、地域の獣医についてインターネットで調べ始めた。
もう夜になっていたので、近隣の獣医リストの口コミなどから「明日の朝、この病院へ行ってみよう!」と心に決めた。子どもたちはもう別の部屋にいたので、明日事情を話して、診断の結果を伝えてあげようと思っていた。
夜遅く、ふたたびマロの様子をそっと見ると、マロがまるで餌入れに寄りかかるように身体をもたせかけているのを発見した。間近に寄って観察し、私は目を疑った。
「これはいったい……どうして……?」片方の足が微妙に宙から浮いていて、身体が微妙に傾いていた。さっきまでは自分の足でしっかり立って、顔を羽に埋めていたのに。
「これではもう……まるで自分を支えることもできなくなってしまったみたいに弱りきって……」私は声も出なかった。胸がどきどきして、名前を呼んでやることもできなかった。「だって、名前を呼んだら、またいつものピィをやろうとして、回復すべき体力を奪うことになってしまうかもしれない……」
不穏な予感におそわれても、具体的になんの助けになってやることもできない無力さとくやしさを感じ、私はなにがマロをこんな状態にしてしまったのかと悩みはじめた。そうやって漠然と考えても、状況はなにひとつ変わらないのは、自分でもわかっていた。私は不安で、混乱していた。「そんなはずはないのだから、きっと回復するのだから」と願う気持ちと、「もうここまできたら、さすがにダメではないのか」という諦めが交互におしよせ、やがて綯い交ぜになった。
深夜、私はいてもたってもいられなっくなって、マロが眠っているケージのところへ息を殺して近づいた。「絶対に見たくない」という思いに、「どうしても見なければならない」という思いがようやく追いつき、私をそこへ連れていった。
ほんのりした暗がりで、マロはやっぱり餌入れに寄りかかってうずくまっていたが、私は彼がすでに虫の息であると知った。
「ほんとうに、どうしてこんなことになってしまったのだろう? なにがいけなかったんだろう? マロは風邪かなにかをこじらせて、急性の肺炎かなにかになってしまったのだろうか? 緊急で獣医に電話し、無理にでもみてもらったほうがよかったのではないか?」
私は夫を呼び、これはもう大変な事態になった、急展開だと伝えた。
夫は血相を変えて、部屋の前に飛んできた。けれども彼は自分の気配を消しきれず、ケージに近づき、眠っているマロをおどろかせた。マロは最後の力を振り絞るようにパッと羽を広げ、ケージの奥へ逃げようとした。しかし羽はもう片方しか開くことができず、お腹のところがズズーと床を引きずった。
(ああ………!!)
私はもう見ていることができず、声をあげたくてもあげられず、死は確実にすぐそばにあることが、だれの目にもあきらかだった。
マロに起き上がる力はなく、羽は半開きのまま、うす黄色の小さな身体が暗いケージの真ん中に横たわり、かすかに上下しているさまがぼんやりと浮かび上がっていた。
混乱の中、ベッドに入り、マロがどうか一命だけはとりとめてくれますようにと、子どものように丸くなって祈った。
☆
翌朝、マロはケージの中で冷たくなっていた。
☆
私は抜け殻のような気分で、メソメソしてばかりいた。
窓の外には野鳥が飛んで、ピィピィとにぎやかに鳴いてた。民家の上にはカラスがいて、山の上には鷹や鳶が旋回していた。この町のだれかの家にはインコやオウム、犬や猫、ハムスターがいるはずだった。はるか遠くの大陸にはライオンだのキリンだの、シマウマだの象だのが大勢群れをなしていた。冷たい海の深くでは、サンマやカツオ、クジラがいまもすいすい泳いでいて、北極には白熊が氷の上をアシカを探して移動している。生きものの総数は天文学的数字であって、それもみんなひとつの命、同じように尊くて、あたりまえのように生きてまた死んでいくのに、私はマロがいなくなって、いつまでもメソメソ心を痛めている。
マロはあのとき私の手に乗り、私はそれを引き受けたのに、どうして彼をこんなに早く死なせてしまったのだろう。
☆
迷ったけれど、子どもたちとも話し合い、ブリーダーのOさんへ正直に報告した。
「ショックです」と第一声があった。
「ショックだけど、あなたのほうがもっとショックだよね」
☆
私はインターネットで「オカメインコ 急死」「cockatiel sudden death」「bird death causes」などと検索した。
これほどまでに若くして亡くなったのだから、なにか原因があるはずだった。人間のように心臓発作も場合によってはあるのかもしれないが、あの苦しそうな姿を見ると、なにがあるはずだと思った。
コンピューターの画面には「中毒」という言葉が表示された。
私は息を飲んだ。
◉テフロンによる中毒:テフロン加工のフライパンなどの製品を過熱させた場合(275度以上で有毒ガスが発生)。
◉住環境の毒:塩素系漂白剤、フェノール、アンモニア、一酸化炭素。ヘアスプレー、デオドラント、香水、芳香剤などの製品。
◉食べものの毒:アルコール、りんごの種、チョコレート、アボカド、トマトの葉、乾燥させた豆、きのこ、玉ねぎ、にんにく、カフェイン、塩など多数、誤食の場合。
◉植物の毒:ポインセチア、シクラメン、福寿草、石楠花など多数、誤食の場合。
◉金属中毒:カーテンレールやワインボトルのカバーに含まれる鉛、宝石などの金属を噛んだ場合。
マロが亡くなる2日前、夫がホットプレートを使って肉を焼いていた。体調が急変するまでの日数や症状を考えると、素人なりにもこれだと思った。ほぼ確かだと思う。
正直、「夫か….!」と思った。あの場所でホットプレートを高温でつかったために、マロは中毒で死んでしまった。「ホットプレートって便利だね」と以前に彼が言っていた。便利なのかもしれないけれど、それは小鳥が死んでしまうほど有毒な、見えないガスを出していたのだ……。
それでも夫を責めるわけにはいかなかった。彼に悪気はまったくなく、知識不足がわざわいした。家がLDKである以上、それはいつか起こりかねないことであったし、私自身もそこにある意味加担していたのだから……。
無知というのは罪なのだ。
☆
原因がわかった以上、私は再度Oさんに電話せざるをえなかった。
「なに、テフロンを空焚きしちまったのか……」
言葉もなかった。私はふたたび謝った。Oさん夫婦が愛情こめて育てた幼鳥なのに、申し訳ない思いでいっぱいです、と……。
すると、Oさんが言った。
「しかたがないよ。あんたも自分を責めたって。だって、ご主人は知らなかったんだからね……。まあ、いろいろなことがあるからなあ……。
うちも昔、二階の空気が下に回っちゃったことがあってね。すぐに換気して、調子の悪くなった子を温めて、なんとか事なきを得たなんてこともあったしね……。観葉植物だって毒なのがあるし。ネットにもいろいろ書いてあるようだけど。
まあさ、あいつらは人間より弱い生きものだっていうことなんだよな、結局。
あの子はもうしかたがないよ。だからあんたももう自分を責めるのはやめて、飼い主として経験を積んでさ。ひとまわり大きくなってよ。それでもし、次の子を飼うってことがあったらなら、次の子を幸せにしてやればいいんだ」
Oさんはほんとうに優しくて、電話口でもらった言葉がじんわり心にしみいった。
☆
あれから、子どもたちと鳥かごをシャワーで丹念に洗った。ケージはたしかに行き場をなくしてしまったが、まだうちのリビングに置かれている。
からっぽのケージを見ていると、マロのことを思い出す。ピィピィとうるさく鳴いてまわるマロの声も、首の付け根を掻いてくれと頭を垂れてせがむ姿も、掻いてやるとウットリとして目をつむる表情も、昨日のことのように覚えている。そして彼が私の手にそっと乗った瞬間も。
☆
マロはもう死んでしまって、彼の身体は土の中で眠っていて、それは穏やかにバクテリアに分解されて、やがて土と一体となり、大地に吸収されていく。
それでもまだ、私はマロがそばにいるような気がしている。
☆